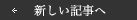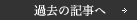「 仏週刊紙襲撃事件で世界が団結でもお寒い日中韓の「言論の自由」 」
『週刊ダイヤモンド』 2015年1月24日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 1068 イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を掲載したフランスの政治週刊紙「シャルリー・エブド」をめぐる言論、表現の自由の戦いの激しさに、私たちは何を読み取るべきだろうか。 事件は1月7日に発生。シャルリー・エブド襲撃で風刺画家5人を含むジャーナリスト8人、全体で12人が殺害された。 11…
「 外交も戦争も全て情報戦が決める 」
『週刊新潮』 2015年1月22日号 日本ルネッサンス 第639回 お正月休みを利用して、以前からじっくり読みたいと思っていた本を読んだ。米国政治学会会長や米国歴史学会会長を歴任し、1948年に74歳で亡くなったチャールズ・A・ビーアドの・President Roosevelt and the Coming of the War, 1941・(邦訳『ルーズベルトの責任 日米戦争はなぜ始まっ…
「 「南京事件」で米国を“洗脳”する習近平政権の邪悪な政治的意図 」
『週刊ダイヤモンド』 2015年1月17日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 1067 1月8日の「産経新聞」が1面で南京事件に関連して、「40万人虐殺」説を伝えた。 これは米国で現在使用されている公立高校の教科書の記述だという。大手の「マグロウヒル」による同教科書には「日本軍は2カ月にわたって7千人の女性を強姦」「日本兵の銃剣で40万人の中国人が命を失った」などと記述されて…
「 中国の脅威による「変化」は日本の好機 」
『週刊新潮』 2015年1月15日号 「日本ルネッサンス」 第638回 昨年暮れ、シンクタンク「国家基本問題研究所」の主催で「戦後70年――国際政治の地殻変動にどう対処するか」と題したシンポジウムを行った。日米中印4か国の論者が参加する予定だったが、前夜祭前日の夜中、突然、中国から出席を見合わせるとのメールが入った。 さまざまな見方が可能だが、何が起きたのかについては推測の域を出ない…
「 15年は安倍政権にとって重要な年 憲法改正に向けた議論の本格化を 」
『週刊ダイヤモンド』 2015年1月10日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 1066 安倍政権と日本にとって、2015年は極めて重要な年だ。14年末に発足した第3次政権の抱負として、安倍晋三首相は「強く誇りある日本」をつくり、「戦後以来の大改革」に「全身全霊を傾ける」決意を表明した。多くの国民が願ってきたことを明言化した決意表明は心強かった。 なぜ、強い日本が必要か。14…
「 特集 安倍晋三×櫻井よしこ 対談 」
『週刊新潮』 2015年1月1・8日合併号 日本ルネッサンス拡大版 第637回 日本経済の「先行き不安」説に答える! 選挙に大勝し、新たな船出を迎えた第3次安倍政権。だがアベノミクスの効果は未だ限定的だ。急激な円安は新たな弊害を生み、再増税先送りで財政再建を絶望視する声もあがる。ジャーナリストの櫻井よしこ氏が、不安渦巻く日本経済の先行きについて、総理に問うた。 櫻井よしこ 選挙での…
「 原油価格急落で窮地のロシアを他山の石にすべき日本の現状 」
『週刊ダイヤモンド』 2014年12月27日・2015年1月3日合併号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 1065 ロシアのプーチン大統領が深刻な苦境に陥り、経済に構造的問題を抱える国の弱さが露呈された。そのことはしかし、膨大な財政赤字でもなお、経済の構造改革に抵抗し、岩盤規制を打ち破れない日本にとって、他山の石でもある。 ロシア経済が自立できない最大の要因はものづく…
「 国民の信を得た今、歴史的使命を果たせ 」
『週刊新潮』 2014年12月25日号 日本ルネッサンス 第636回 衆議院議員選挙の前日まで、新聞各紙には自民単独で3分の2を超える317議席以上という数字が躍り、自民党300議席超えが半ば確定的に報じられていた。結果、自民党は2議席減の291だった。 予想されていた勝ち振りが余りに華々しかったために、意外の感を抱いてしまうが、この数字は、しかし、たしかに自民党の圧勝なのである…
「 強過ぎれば抑えにかかるのか 振り払えない米国への疑惑 」
『週刊ダイヤモンド』 2014年12月20日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 1064 タカタ製のエアバッグ問題が全世界に広がりつつある。作動時に破裂して金属片をまき散らす問題でタカタの対応を見るにつけ、約3年前にトヨタ自動車がどれだけひどい目に遭ったかを思い出してしまう。 私はこの問題を直接取材したわけではなかったが、「ニューヨーク・タイムズ」や「ウォールストリート・ジャ…
「 「弱い日本」を望む米国の反日言説 」
『週刊新潮』 2014年12月18日号 日本ルネッサンス第635回 ペリー率いる黒船4隻は砲艦外交でわが国に開国を迫ったが、その後、日米関係はあからさまな敵対関係に陥ることなく基本的に友好関係を維持し、交易を拡大させた。明治38(1905)年、日本が日露戦争に勝ったとき、セオドア・ルーズベルト大統領は日本の勝利を喜び、ポーツマスでの講和条約の交渉を後押しして、ノーベル平和賞を受賞した。 …