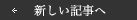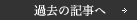「 中国による第三世界の核拡散 」
『週刊新潮』 2009年7月30日号 日本ルネッサンス 第372回 中国はかつてソ連と袂(たもと)を分かって、自力で核を開発した。後発国の中国の核開発のスピードに、世界は驚いたが、その裏には多くの葛藤があった。また、中国は核兵器を第三世界に広げるべく、核関連技術を複数の国々に輸出したのみならず、フランスに核実験場を提供し、フランスの核にも協力していた。 中国の核政策の実態は驚きである。中国…
「 ウイグル弾圧、国連で公平な調査を 」
『週刊新潮』 2009年7月23日号 日本ルネッサンス 第371回 中国新疆ウイグル自治区の区都ウルムチで大規模暴動が発生して、1週間程が経った。胡錦涛国家主席は8日、サミット出席のために訪れていたイタリアから急遽帰国し、同日夜に中国共産党中央政治局常務委員会を緊急招集した。 中国の最高意思決定機関である常務委員会は、ウルムチの暴動は、海外の分離独立勢力が画策した犯罪だと決めつけた。画策に乗っ…
「 CO2と気温の関係に新説 気温上昇がCO2増加に先行する 」
『週刊ダイヤモンド』 2009年7月18日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 797 麻生太郎首相は、2020年までに温室効果ガスの排出を05年比で15%削減すると決定した。省エネも、CO2削減も大いに結構だ。しかし、政府の政策は合理的なのか、国益にかない、国際社会への真の貢献につながるのか、疑問である。 右の目標達成には、約62兆円の投資が必要とされる。一方、05年…
「 藩校サミット、現代の殿様勢揃い 」
『週刊新潮』 2009年7月2日号 日本ルネッサンス 第368回 6月20日の土曜日、新潟県長岡市で、かつての大名家の末裔の方々30人が集い、「藩校サミット」が開かれた。藩校サミットは、2002年に、「日本の学校教育発祥の地」ともいわれる、東京お茶の水の湯島聖堂で始まった。 時代が変われば人も事物も変わるとはいえ、あまりにもいまの日本は日本らしくない佇まいになってしまった。だからこそ、かつ…
「 CO2、政府はもっと賢い削減策を 」
『週刊新潮』 2009年6月25日号 日本ルネッサンス 第367回 6月10日、麻生太郎首相は官邸でパネルを示しながら会見し、2020年までに温室効果ガスの排出を05年比で15%削減すると発表した。 中期目標としての15%削減を実現するには、産業、家庭、運輸などの各分野で総額62兆円もの省エネ関連の投資が必要とされる。目標達成の具体策は、太陽光発電の導入量を20年までに20倍にす…
「 力で攻める中国に心で戦うチベット 」
『週刊ダイヤモンド』 2009年6月6日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 791 ケルサン・ギャルツェン氏は、チベット亡命政府特使として2002年以降、中国側との接触を重ねてきた。 「公式の接触は8回、非公式は1回です。ダライ・ラマ法王の求めは、主として3つ、国際社会の倫理に沿う人権の推進、宗教に基づく和の確立、チベット人の価値観の擁護と存続です。政治的要求を出したことはあ…
「 拉致被害者、横田めぐみさんをなぜ北朝鮮は必死に隠すのか 」
『週刊ダイヤモンド』 2009年5月16日号 新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 788 4月25日のテレビ朝日の「朝まで生テレビ」で「横田めぐみさんも有本恵子さんもすでに死亡している」と、総合司会の田原総一朗氏が、“外務省二番目か三番目”の高位の人物の情報として、語ったそうだ。恵子さんのお父様の有本明弘さんが怒っていた。めぐみさんのご家族も、その他の拉致被害者のご家族も、同じ思いだった…
「 日韓歴史問題を解くか、新分析 」
『週刊新潮』 2009年3月26日号 日本ルネッサンス 第355回 韓国の対日歴史観を根底から変えるきっかけともなる本が出版された。ソウル大学経済学部教授、李榮薫(イヨンフン)氏の『大韓民国の物語 韓国の「国史」教科書を書き換えよ』(文藝春秋)である。 昨年7月、韓国で会ったとき、教授は『物語』の下書きともいえる『代案教科書』という本を、同僚の教授らと共同執筆したばかりだった。『代案』では…
「感情的反捕鯨論との闘い方」
『週刊新潮』 2009年2月19日号 日本ルネッサンス 第350回 2月6日、南極海で調査捕鯨船「第二勇新丸」が米国の反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)の抗議船に体当たりされ、母船の「日新丸」には、目に入ると失明の恐れがある酪酸入りの瓶が投げ込まれた。 国内では、かつて外務副報道官を務めた谷口智彦氏の『WEDGE』09年2月号での主張をはじめ、日本は調査捕鯨から撤退すべきだとの意見が発表さ…
「 分裂と漂流、アラブ世界の実態 」
『週刊新潮』’09年2月12日号 日本ルネッサンス 第349回 原油輸入で、日本が圧倒的に依存する中東情勢の展望が危機的なまでに不透明だ。日本は中東政策でも米国に頼ってきた。結果、日本の国益を軸にした中東外交の基盤は未だ確立されていない。日本の中東政策はいかにあるべきか。 中東調査会の大野元裕氏は中東で起きている“2つの分裂”を理解することが重要だと述べる。2つの分裂への理解なしには、イ…